10月に開通した北海道横断自動車道のトマムIC-清水IC間を体験してきました。
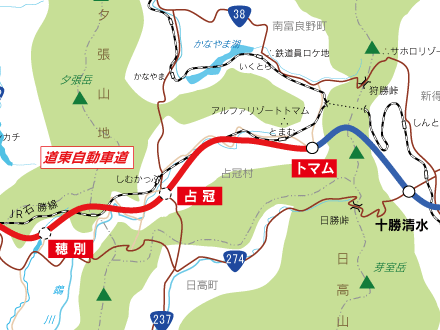
この区間は魔の峠とも呼ばれる日勝峠の代替として期待されていた区間で、日勝峠を走らずに十勝方面へ抜けれるということは道東に住む人にとって結構悲願だったんです。
ひとたび日勝峠で霧が出たり、吹雪いたりすればそりゃあもう大変だったんですよ。
で、今日、実際走って来たので感想を書いてみたいと思います。
○良かったこと
トマムICから高速に乗るとすぐに「南富良野町」の看板があり、二つ目のトンネルの入口手前に1600m先新得町の看板がありました。
トマムICから高速にのってものの数分で十勝支庁に入ってしまいました。
「え?もう十勝?日高山脈ってこんなに簡単に抜けていいんだっけ?」
って感じです。
また、道路自体も緩慢なカーブで構成されていて、ブレーキを踏む必要性をまったく感じませんでした。
広大な牧場の中を高速道路が走っているという感じで、なんというかドイツのアウトバーンってこんな感じなんでしょうか。走ったことないけど(笑)
冬もきれいだったけど、フォーシーズンきれいなんだろうなって感じです。
×悪かったこと
これは実は4年後には解決される問題なのですが、札幌方面からアクセスすると、石勝樹海ロードの穂高峠を降りたところから左折して、赤岩トンネル方面に向かいます。
この道が余りよくない。
川沿いの道ということもあってコーナーが多すぎます。また、日陰になっている場所もけっこうあって凍結していることが多そうです。
また、274号線からトマムICまで約40Kmもあり、その長さが結構不満な感じでした。
しかし、この問題も未開通の紅葉山-占冠間が4年後に開通すれば解決するわけですから、大きな問題ではなさそうです。
しかし、最近の政治ものワイドショーなんかみていると地方に道路を造るのは無駄遣いだというような観点から番組作りをしているのが非常に多いですよね。
これって僕にはとても違和感があります。
たしかに某建設族のドンの地元の県に異常に道の駅が多いなんて話を聞くと、無駄遣いの極みだなと思います。あんなのはPFIかなんかで民間活力を使ってやればいい。
しかし、高速道路のネットワーク自体は国土の均衡の発展のためにはどうしても必要だと思うのです。
効率性だけを求め、地方がいらないというのであれば、地方の道路をつくるのはたしかに無駄でしょう。しかし、たとえば医療の問題ひとつ考えてみても、高度医療を受けられる拠点病院まで車で2時間程度の場所でないと、やはりなかなか住むことは難しい。
だから道路ネットワークが不要だということは、そういう道路のない地方にすんでいる人に対し、生きるな(病気になったら死ね)と言っているのと同じことだと思うのです。
食糧安保の問題を考えていても、国民の食を安全にしたいと思うのであれば、せめて主食は海外からの輸入を減らし、国産で安全なものを生産しなければならない。
そのためには、やはり地方がそれなりに経済的な競争力を持ちうるように、最低限必要なインフラストラクチャを整備することはたとえ非効率であっても中央政府の責任であると思うんです。
その上で地方政府は地方の魅力を増やすために力を尽くしていく。だから、これからは地方政府の責任もますます重大になっていきます。
それが本当の地方分権ですし、そのためにはもっともっと地方政府に優秀な人材が集まらなければならない。
ただ叩けばいいと思っている人は基本的に考えが浅い。
報道する人は、そういう対極的な視点からもものを考えてほしいと僕は思います。
#道路ひとつの話から、ずいぶん話が大きくなってしまった^^;